わが子の特性と出会いなおすまで
息子が発達検査を受け、「成長にでこぼこがある」と言われた日。
その言葉は、私にとって初めて「息子らしさ」を捉えるヒントになりました。
でもすぐに納得したわけではありません。
少しずつ、日々の困りごとと向き合いながら、その“でこぼこ”の輪郭を確かめていった日々を、今日は振り返ってみたいと思います。
でこぼこ、ってどういうこと?
「成長にでこぼこがある」──発達検査で言われたとき、正直ピンと来ませんでした。
確かに、息子には「困っていること」がいくつもあったけれど、
できること・できないことを並べてみても、「そんなに差があるのかな?」という感覚もあったんです。
でも日々の生活の中で、少しずつ見えてくるようになりました。
「できる時」と「できない時」の差が激しい
うちの息子には、「できる時とできない時の差が大きい」特徴がありました。
- 昨日はできたのに、今日は無理。
- 朝はできたのに、夕方はパニック。
それが「気分の問題」じゃなくて、「感覚」や「こだわり」が影響していると気づいたのは、何冊か本を読んでからでした。
最初に読んだ本で「うちも当てはまるかも」と思ったものの、
腑に落ちるにはもう少し時間が必要で、何冊か読んだあとにようやく「ああ、これか」と思えました。
わがまま?イヤイヤ期?──誤解していた時期
ちょうどイヤイヤ期とも重なっていたこともあり、
最初は「これはわがまま?」と思ってしまったことも多かったです。
- 指定の靴下じゃないと履かない
- 洋服のタグが気になる
- 触られるのを極端に嫌がる
これが「こだわり」や「感覚過敏」だと理解するまでには、私にも時間がかかりました。
苦手を理解すると、見えてきたこと
「得意を伸ばそう」と思っていた時期もありました。
でもそれは、どこかで「苦手を乗り越えて」得意を見つけようとしていた気がします。
今は、無理に得意を見つけようとしなくてもいい。
まずは「苦手なことを減らしてあげたい」──
そう思えるようになってきました。
たとえば:
- 感覚過敏で苦手な音にはイヤーマフを
- 着る服の素材を一緒に選ぶ
- 無理な外出はやめてスケジュールに余白を
そんな小さな工夫で、少しずつ「ご機嫌な時間」が増えてきたんです。
💬まとめ:でこぼこの形はいろいろ
もし、今まさに「わからない」「理解できない」と悩んでいる方がいたら、
「でこぼこ」という言葉を、そっと心に置いてみてほしいです。
私たち親も「成長途中」です。
焦らず、ゆっくり、でこぼこの形を見つけていけたら──
それで十分だと思えるようになりました。
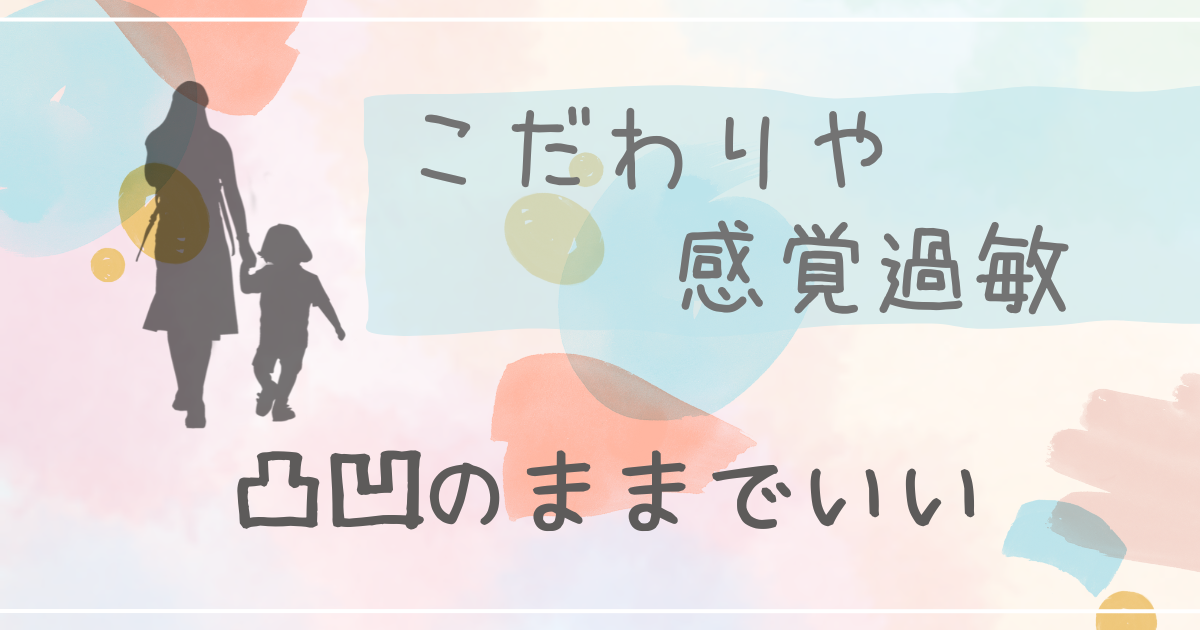

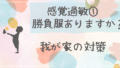
コメント